花粉も飛び始めて、鼻水や鼻づまり、だるさなどの症状が出てきた方もいらっしゃるのではないでしょうか?
それに加えて、目のかゆみや充血など、目の症状もつらいですよね。 そこで今回は、花粉症の目薬について薬剤師に解説していただきました。
処方薬と市販薬の違い
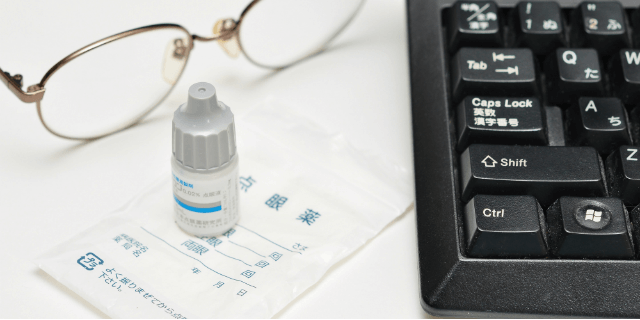
処方薬とは、「医療用医薬品」のことで、医師の処方箋と薬剤師の指導が必要な薬です。病院でもらう薬ですね。
安全性や副作用の危険、乱用を防ぐためにも、処方薬は医師、薬剤師の定期的な管理が必要です。
一方で市販薬とは、「一般用医薬品」のことで、ドラッグストアなどで処方箋なしで買える薬です。要指導医薬品と第1〜第3類医薬品に分類されます。
安全性が高く、副作用の低いもので、処方薬と同等の成分である場合や、濃度を薄くしてある場合もあります。
市販の目薬のメリット

市販の目薬は効果が少ないのではないかと考えられがちですが、そんなことはありません。
基本的に、処方される医療用目薬は1薬品1成分です。医師が患者さんに合わせて処方するためには、合理的な作りになっています。
一方で市販の目薬の魅力は、各メーカーが知恵を絞って1本の目薬に複数の成分がブレンドしてある所です。
市販の目薬には、診察を受ける時間がないときに手軽に買えること以外にも、何種類かの成分を同時にさせるというメリットがあります。
市販の目薬の選び方

花粉症で使われる目薬は、主に以下の3つです。
【抗アレルギー薬】
代表的な成分:クロモグリク酸ナトリウム(ヒスタミンの発生を予防する)
【抗ヒスタミン薬】
代表的な成分:クロルフェニラミンマレイン酸塩(ヒスタミンの活動を抑える)
【ステロイド薬】
※ステロイド目薬は、処方薬のみで市販されていません。
市販の目薬では、その内、抗アレルギー薬と抗ヒスタミン薬のどちらか、または両方に抗炎症など他の成分をブレンドしてあるものが多いです。
花粉症で市販の目薬を選ぶときは、「クロモグリク酸ナトリウム」もしくは、「クロルフェニラミンマレイン酸塩」という成分が入っているものを選ぶとよいでしょう。
どれがよいか迷ったときは、薬剤師に相談することをおすすめします。
共に効き目が出るまでに少し時間がかかるため、最低でも1週間は使ってみてください。
※ 重要
緑内障など目を治療中の方は、目薬を併用してよいか必ず医師に相談してください。治療に影響する恐れがあります。
充血がひどい場合は、充血用の目薬を併用して構いません。ただし、花粉症の目薬によっては既に充血に対する成分が含まれていることもあります。成分が重複していないかチェックが必要です。
目の充血には血管収縮剤を用いますが、リバウンドを防ぐためにも日頃からの連用は避けましょう。
目薬を使う際の注意点
以下は、花粉症用に限らず全ての目薬共通の注意点です。

複数の目薬をさす際に、順番はある?
目薬を2種類以上使う場合、特に指示がなければ、順番はどちらが先でも構いません。
同時に使う場合は、間隔を5分以上空けてください。後に使う目薬で、先に使った目薬が流れないようにするためです。
ドライアイなどで懸濁性、油性の目薬を使用する場合は、後にさしましょう。
目薬は何回さしてもいい?
副作用のリスクが高まる恐れがあるため、回数制限を守りましょう。
目薬に使用期限はある?
特に指示がない場合、目薬は開封後「処方薬は1カ月」、「市販薬は3カ月」が使用期限の目安です。
花粉症の場合、次のシーズンには期限が切れるため、ご注意ください。
目薬の保管は冷蔵庫のほうがいい?
市販の目薬は、基本的に常温保管です。直射日光と高温を避ければ、特に冷蔵庫に入れる必要はありません。
遮光袋がついている製品は、遮光の必要性があります。迷ったら点眼袋に入れて保管してください。
処方された目薬など、冷所保管の指示があった場合は、凍結を避けて冷蔵庫へ入れてください。
子どもが使ってはいけない目薬はある?
市販の目薬の場合、年齢制限を確認しましょう。自身で症状、さし心地を伝えられない年齢のお子さんは、医師の診断を推奨します。
目薬以外の対処法

辛い目のかゆみには、以下の方法を試してみてください。
・目をこすらない
・濡れタオルや保冷剤をくるんだタオルで目を冷やす
・人工涙液などで目を洗う(防腐剤の入っていないものが望ましい)
花粉の付着を極力避け、目の炎症を起こさないよう気をつけましょう。
コンタクト使用中の方

コンタクトの使用で、花粉症の症状は悪化しやすくなります。レンズ汚れに、花粉がピタッとくっつきやすくなるためです。
できるだけコンタクトの使用頻度を減らすか、コンタクトは毎日きっちり洗うように心がけましょう。
また、目薬によってコンタクトを装着したまま点眼できるものと、外す必要があるものに分かれます。使用上の注意をよく読んで確認しましょう。
コンタクトを外す必要があるものは、点眼後、装着までに5〜10分程度空けてください。
最後に薬剤師から一言
花粉症の目薬は、効き目が出るまでに多少時間がかかるため、早めに使用を開始しましょう。1〜2週間使用しても、症状が改善しない場合は眼科に受診をおすすめします。
受診の際には、目薬を含めて、使用中の薬を医師・薬剤師にお伝えください。
お薬手帳には処方薬だけではなく、使用している市販薬や健康食品も書き込んで、ぜひ健康管理に役立ててくださいね。
プロフィール
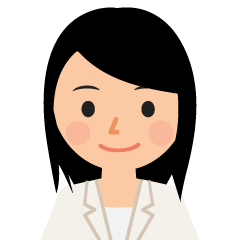
- 監修:薬剤師 吉田
- 大型病院前の調剤薬局を数店経験し、薬の副作用・飲み合わせや食事指導、お子さんへの薬の対応など広く携わる。 また、感染症と漢方分野に強く興味を持ち、積極的に学会や講演会に参加。現在ヨーロッパ在住。

