献血を受けたことってありますか?受けてみたいけどよく知らないから不安…せっかく行ったのに献血を断られた…という方もいるでしょう。
そこで今回は、知っているようで知らない献血について井上先生に解説していただきました。
献血ってなんで必要なの?

医療現場では、病気やけがで血液が必要な人に対して、輸血する場面があります。
これだけ医療技術が進んでいても、人工的に血液を作り出すことはできません。そこで、必要になってくるのは献血です。
輸血で使う血液製剤は、献血で提供された生きた細胞の血液をベースにして作ります。そのため、献血で得た血液は長期的に保存することができず、輸血などで使用できる血液が不足しがちになっています。
街頭で献血の呼びかけが多く行われているのも、このような理由からです。
献血に種類があるって本当?

献血と一言でいっても、色々な種類があります。まずは大きく、「全血献血」と「成分献血」に分けることができます。
全血献血
全血献血とは、そのままの血液を提供する献血です。血液中の特定の成分だけ採取するわけではありません。
全血献血では「200 ml」か「400 ml」か、提供する血液量によってさらに分けることができます。
・200 ml全血献血
海外では、400 mlの血液を提供する献血が主流です。一方日本では、日本人の小柄な体系に合わせた200 ml全血献血があります。これは、献血制度ができたときからある種別です。体への負担が一番少ないと考えられており、16歳から参加できます。
体重に関しては、女性であれば40 kg、男性であれば45 kg以上で受けることが可能です。
・400 ml全血献血
400 ml全血献血を受けるのであれば、男女ともに50 kg以上の体重が必要です。
400 ml全血献血が必要となる理由として、たとえば、800 mlの輸血が必要になった場合、4人から200 mlずつの提供を受けるよりも、2人から400 mlずつのほうが輸血される患者さんにとって副作用が少ないという点が挙げられます。
成分献血
成分献血とは、血液中の「血漿」や「血小板」といった成分のみを提供する献血です。輸血を受ける患者さんにとっても不必要な成分が体に入らないため、より副作用が起こりにくいと考えられています。
また、成分献血は成分によって、「血漿成分献血」と「血小板成分献血」に分かれています。
「血漿」は、血液中の約半分を占めており、体内の各臓器に酸素や栄養素を運び、老廃物は腎臓に運ぶなどの役割があります。
「血小板」には、血管が破れたときに血管を塞ぐ役割があります。
成分献血に関しても体重での制限があります。女性は40 kg以上、男性は45 kg以上が必要です。
献血ができない人はいる?

実は、献血は誰でも受けられる訳ではありません。上記で記載したように、年齢、性別、体重によって受けられない献血種別もあります。それ以外にも、下記に該当する方は献血を断られる可能性があります。
・特定の病気にかかったことがある
・過去に輸血や臓器移植を受けたことがある
・エイズ、肝炎などのウイルス保有者、または疑いのある方
・妊娠中、授乳中、発熱中など
・服薬中(薬の種類にもよる)
・過去にプラセンタの注射薬の使用したことがある
・AGA治療でフィナステリドを内服中
・3日以内に出血を伴う歯科治療(抜歯、歯石除去など)を受けた
・一定期間内に予防接種を受けた(予防接種の種類にもよる)
・4週間以内に海外から帰国(入国)した
・6カ月以内にピアスの穴をあけた
・6カ月以内にタトゥーを入れた
献血の所要時間はどれくらい?

全血献血では、200 ml献血でも400 ml献血でも15分くらいで終了します。しかし、成分献血の場合は、特定の成分のみ提供してもらうため、全血献血よりは所要時間が長くなります。
採血量によっても変わってきますが、40分~90分程度で終了することが多いです。
献血をするメリットはある?
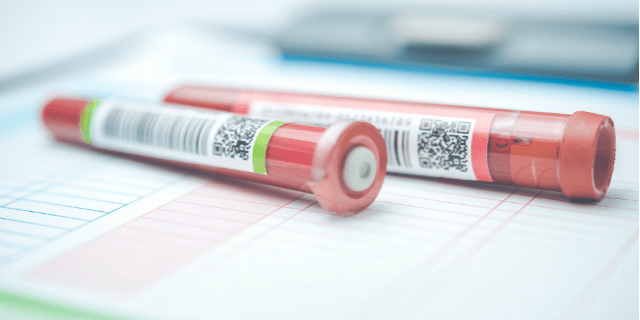
献血はボランティアなので、メリットなどを考慮すべきではありません。しかし、実際は献血をした方にもプラスになります。
たとえば、献血していただいた方には、血液検査の結果が渡されます。もちろん測定項目は限られていますが、健康診断でよくみかけるような項目の多くがカバーされていますよ。
最後に井上先生から一言
「献血」という言葉を聞いたことがある方はたくさんいるでしょう。
しかしながら、輸血に使用する血液が、これだけ医療技術が進んだ現在でも、人工的に造ることも長期的に保存することもできないことまで知っている方は、意外と少数でしょう。
ですから、どうしても本当に必要な血液が不足した状態が続いております。1人でも多くの協力が必要ですので、よろしくお願いします。
プロフィール

- 監修:医師 井上 智介
- 島根大学を卒業後、様々な病院で内科・外科・救急・皮膚科など、多岐の分野にわたるプライマリケアを学び臨床研修を修了する。 平成26年からは精神科を中心とした病院にて様々な患者さんと向き合い、その傍らで一部上場企業の産業医としても勤務している。

