待ちに待った夏休み!旅行にキャンプ、夏祭りと外に出かける機会も多くなりますよね。そこで注意したいのは虫刺されです。
今回は、夏に注意しておきたい虫刺されについて、建部先生に教えていただきました。
(1)蚊
特に注意したいのは、海外で蚊に刺されたときです。長らく日本で確認されてこなかったデング熱が流行したように、蚊は病気を運びます。
東南アジアやアフリカ方面などでは、以下の蚊が原因となる病気がみられます。
・黄熱病
・デング熱
・マラリア
・フィラリア
・ウエストナイルウイルス熱症
・チクングニア熱
・ジカ熱 など
世界的に問題となっているジカ熱については、近年、東南アジア諸国でも発生が確認されています。ジカ熱の原因となるジカウイルスは、神経障害の発症や、妊婦さんへの感染により胎児へ影響を及ぼすことが明らかとなっており、注意が必要です。
蚊に刺されたときの対処法
かゆみに対しては、市販の外用薬などで様子を見て、改善しない場合は受診しましょう。海外旅行で蚊に刺された後に高熱が出た場合は、受診してください。
蚊が媒介するデング熱、ジカ熱などは、今のところ予防ワクチンはありません。そのため、「蚊に刺されないこと」が効果的な予防法です。長袖・長ズボンをできるだけ着て、虫よけスプレーを使ってください。
(2)アブ
アブは、牧場や山などでよく見かけるハエの仲間です。真っ黒なハエのような「ヤマトアブ」や見た目が少しスズメバチに似た「アカウシアブ」などが、吸血性のアブとして知られています。
ハチとは異なり、吸血性のアブはヒトや動物の血液を目的にしているため、しつこくついてきます。刺された瞬間はチクッと痛みがあり、刺された後は強いかゆみを伴います。
アブは蚊のようにウイルスや細菌をヒトや動物に媒介しているという事実は、今のところ確認されていません。
アブに咬まれたときの対処法
(1)咬まれた部分を流水で洗い流す。消毒液で傷口を消毒する。
(2)咬まれた部分を軽く押して皮膚の下の液(アブの唾液など)を出す。(※口で吸い出すのはNGです。)
(3)「痛み」「腫れ」「かゆみ」がある場合は、冷えた缶ジュースなどで噛まれた部分以外の炎症を起こしている部分に軽く押し当てて冷やす。
(4)「痛み」「腫れ」「かゆみ」が長引くようであれば皮膚科を受診し、抗ヒスタミン薬やステロイド薬を刺された部分にできるだけ触れずに使用する。
※咬まれた直後にスーッとする成分(メントール)が含まれた塗り薬を使うと、皮膚の下の粘膜を刺激するため控えましょう。
(3)ブヨ

ブヨは、アブと同じくハエの仲間です。大きさは約3~5 mmです。
吸血直後は、咬み切られた部分を中心に赤い出血点や微量の出血、水ぶくれが現れます。ブヨは唾液腺から毒素を注入するため、翌日以降に患部が赤く膨れ上がります。蚊やアブに刺された後とは比較にならないほどの激しいかゆみや疼痛、発熱などの症状が1~2週間ほど続きます。かゆみについては、2週間以上治まらないこともあります。
多く吸血された場合は、リンパ管炎やリンパ節炎を併発し、呼吸困難など重篤な状態に陥ることもあります。ブヨに咬まれたことがはっきりしている場合は、皮膚科に速やかに受診してください。
ブヨに咬まれたときの対処法
ブヨに咬まれたときの対処法は、アブの場合とほぼ同じです。そして、かゆみに対しては「掻かないことが非常に重要」です。掻くと腫れが一向に引かなくなり、治ったあともシミとして残ります。
ブヨは、山間のきれいな川の渓流などに生息しています。これらの場所で朝夕の涼しい時間帯を過ごすときは、肌の露出を避け、ブヨに効く虫除けスプレーを使用し、特に注意しましょう。
(4)トコジラミ

トコジラミは、ダニに似た小さなカメムシの仲間で、ヒトや動物の血を吸います。南京虫やベットバグとも呼ばれます。成虫は5~8 mmで、体は丸く扁平で褐色です。触れるとカメムシと同じようにいやな臭いを出します。
日本では目にすることの少なくなったトコジラミですが、今でも被害はときおり発生しています。トコジラミは、ヒトの荷物や輸送される家具などに取り付くことで、分布を拡大します。
マットレスやシーツ、壁、柱、本などに、黒~赤褐色の点のようなフンを発見したらトコジラミを疑ってください。トコジラミは、明るい場所にあまり出てこず、主に夜間に活動します。寝ているヒトの手、足、首など、露出部分を複数刺します。
刺されると肌に赤い斑点(1円玉くらいの大きさ)ができ、夜も眠れないほどのかゆさを感じます。個人差もありますが、痕は1~2週間以上残ります。また、リンパ節の腫れや発熱を伴う場合もあります。
トコジラミに刺されたときの対処法
市販されている抗ヒスタミン剤入り外用薬を使いましょう。改善がみられない場合は、早めに皮膚科を受診しましょう。
(5)ハチ

すべてのハチがヒトを毒針で刺すわけではありません。ヒトを刺すハチには、スズメバチ、アシナガバチ、ミツバチなどが挙げられます。
ハチ毒には、微量でも痛みを引き起こす「アミン類」「低分子ペプチド類」などが含まれています。これらの物質を一番多く含んでいるのは、スズメバチの毒です。
ハチ毒にアレルギーがない場合は、患部に激しい痛み、腫れ、時にかゆみなどが起こります。数日で症状が和らぐ局所症状のみになります。
ハチ毒にアレルギーがある場合は、局所症状だけではなく、全身症状を呈する場合があります。全身の蕁麻疹や頭痛、発熱、嘔吐、めまい、息苦しさなどを伴います。さらに刺されて15分~1時間以内に血圧の急激な低下、呼吸困難、意識障害などに移行すると、命に関わるアナフィラキシーショックを起こすことがあります。
特にハチに刺された経験が2回目以降では、アナフィラキシーショックを起こすリスクが高いです。
ハチに刺されたときの対処法
ハチに刺された場合は、流水で毒液を絞り出すようにして洗い流します。症状の有無や程度を問わず、速やかに受診してください。
建部先生からのアドバイス
夏になると、レジャーで山や海、海外にお出かけすることが多いと思います。蚊やアブ、ブヨなどがいそうな場所に出かける際は、肌を露出しないように長袖・長ズボンを着用し、虫よけスプレーを使うことが大切です。
ハチ以外の虫刺されには、かゆみがついて回ります。休日夜間の場合は、応急対応しかできません。我慢せずに、できるだけ昼間のうちに皮膚科を受診しておくことをおすすめします。
プロフィール
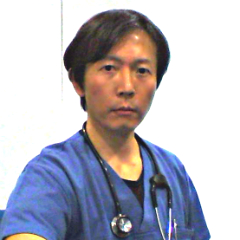
- 監修:医師 建部 雄氏
- 京都市生まれ。社会人を経て医師を志す。2001年、昭和大学医学部医学科卒業。 卒後、東京都内の大規模総合病院にて救急科の経験を積む。 その後、阪神淡路大震災において内科医が避難所等で切実に必要とされていた事実を知り、より多くより幅広く患者さんに対応できる医師を目指して総合内科へ転向を決意。 急性期病院・クリニックの勤務を経て、最も身近な医師としての研鑽を積んでいる。 現在は、横浜市内の総合病院に勤務中。週末を中心に休日夜間の非常勤先病院 救急外来勤務をほぼ趣味としており、失敗も成功も含めて経験は豊富。

