子どもの苦手な食べ物の中の一つに、魚が挙げられることが多いようです。
魚は骨も多く、食べづらさなどが原因になることがありますが、栄養価も高いので親としては残さず食べて欲しいですよね。
今回は、子どもの魚嫌いを克服させるために、苦手な原因を掘り下げ、オススメの魚の種類やレシピを栄養士の横川先生にお話を伺いました。
目次
子どもに魚を食べさせるのは何歳くらいから?

子どもに魚をあげる目安は、離乳食5、6カ月頃。しらす干しやちりめんじゃこのすりつぶしから可能です。
また刺身などの生の魚をあげる目安は胃腸も発達し、離乳食もほぼ完了した2歳くらいと言われています。
しかし、与える際は、何かあれば直ぐに対応できる病院が空いている午前中に、少量ずつ与えてみるのが良いでしょう。
魚の代表的な栄養成分

たんぱく質
お魚に含まれるたんぱく質は、必須アミノ酸をバランスよく含むため、体内で吸収・利用されやすいのが特徴。そのため、成長期に欠かせない成長ホルモンの分泌に役立ちます。
オメガ3系脂肪酸(DHAやEPA)
脳の機能を高め、血中のコレステロールや中性脂肪をコントロール、子どもの生活習慣病を予防する働きが期待できます。
カルシウム
骨や歯の成長に欠かせない栄養素。成長期に不足すると大人になった時に骨粗鬆症になりやすい心配が。
子どものうちからコツコツ積み重ねて摂取していくことが肝心です。
亜鉛
味を感じるセンサーである味蕾に関わっており、子どもの味覚の成長に重要な栄養素。
その他、たんぱく質の代謝や、骨の成長に関係しています。
鉄
私たちの体に必要不可欠な酸素。鉄は、そんな酸素を体中に運び届けてくれるヘモグロビンの原料となります。
鉄不足は集中力の低下や、貧血、免疫力の低下などに。
タウリン
脳内では神経伝達物質として働くため、脳の発達をサポートします。
子どもが魚嫌いになってしまう原因
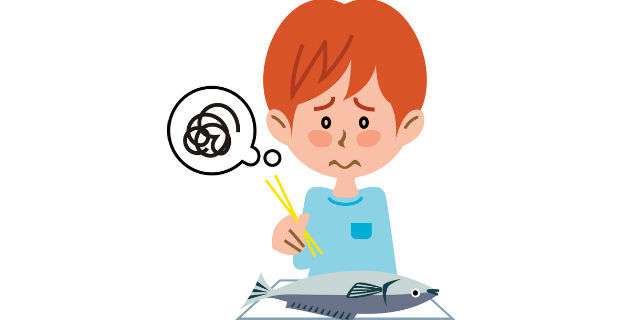
骨がある
魚料理は骨をとるひと手間が必要。子どもはまだ手先も器用でないこともあり、骨をとる作業が苦手、その結果、魚を嫌煙しがちに。
独特の魚臭さや苦みが嫌い
魚の水分から出る生臭さや、内臓周辺の苦みに敏感で嫌いになる子がいます。
食感が苦手
魚料理のパサパサした食感が苦手で食べないことも。
大人があまり食べていない
今では大人でも魚を食べる機会が少ないため、その結果食べ方がわからなかったり、馴染みがない事で食わず嫌いになっている子もいます。
(参照:水産庁)
子どもが嫌いな魚の種類

子どもが嫌いになりやすい魚は、サバ、サンマ、あじ、いわしなど青魚系。
その理由に、これらの魚は鮮度が落ちやすいため独特の生臭さが出やすく、小骨も多いことが挙げられるでしょう。
子どもが好きな魚の種類

子どもが好きな魚は、離乳食から食べやすいシラスや、刺身の人気商品でもあるまぐろやサーモンなどが挙げられます。
特にまぐろは、やわらかく独特のくさみがないため、食べやすいと感じている子が多いと考えられます。
子どもの魚嫌いを克服させるポイント
臭い対策

・ 新鮮な状態なものを使う
・ 苦みがある内臓や臭みに繋がる血液を取り除いたりと、しっかり下処理を行う
・ ハーブ、香辛料、調味料などを利用して臭いを緩和する
骨対策

・ 親が骨をとってあげたり、身をほぐしてあげる
・ 骨がないしらす等、食べやすい小魚から食べさせる
メニュー対策

・ お寿司など子どもの好きな料理から親しみをもってもらう
・ 缶詰を利用する
・ ハンバーグなど魚の形がわからないように、好きな料理に混ぜる
苦手意識対策

・ 無理強いしない、少しずつ慣らしていく
・ 魚のせんべいなど子どもが食べられそうなおやつからはじめる
子どもの魚嫌い克服レシピ

カルシウム補給にも!骨ごと食べやすいししゃもの磯部揚げ
■ 材料 (子ども:2~3人分)
・ししゃも:6尾
・(a)青のり:大さじ1
・(a)粉チーズ:大さじ1/2
・(a)乾燥パセリ:大さじ1/2
・揚げ油:適宜
【衣】
・小麦粉:大さじ2
・冷水:大さじ3~4
【飾り】
・レモン
■ 作り方
1. 破裂を防ぐため、ししゃものお腹を爪楊枝で2、3箇所突き刺し穴を開ける。
2. 小麦粉を冷水で溶き(a)を混ぜ、ししゃも全体によく絡める。
3. 170℃の高温の油で揚げる。
4. お皿に盛ってレモンを添えたら、出来上がり。
■ ポイント
ししゃもは丸ごと食べやすい魚ですが揚げることで更に骨っぽさが軽減し、食べやすくなります。
◎小麦粉と水で衣を作るのが難しい場合は、天ぷら粉を代用すると良いでしょう。
◎衣はトロッとするくらいに混ぜ合わせる方が青のりのつきが良いです。
◎衣はベーキングパウダーを少々入れるとふわっとした衣になります。
◎幼児の場合は1尾程度を目安に。奥歯が生えそろっていなければ荒くほぐしてあげると良いでしょう。
最後に横川先生から一言

私の娘はサンマを食べられるのですが、あまり食べたがりません。
「どうして?」と理由をきくと「骨が多いから」と答えていました。骨が多いと身を食べるのに時間がかかってしまうので抵抗があるとのこと。
子どもはちょっとした理由でも選ばないことも多いですが、食べない=嫌いというわけでもないため、食べない理由を聞いてまずは食べられるのであれば缶詰やかば焼きなど骨ごと食べやすい料理から親しみをもってもらうのが良いでしょう。
プロフィール
- 監修:栄養士 横川 仁美
- 食と健康・美容を繋ぐ「smile I you」代表。 お味噌汁レシピ研究家×薬機法に強いセールスライター。 管理栄養士を取得後、保健指導や重症化予防、ダイエットサポート、電話相談のカウンセリング等を通して、のべ2000人の方の食のアドバイスに携わる。現在はコラム執筆・監修、レシピ作成、オンラインでのダイエットカウンセリングを中心に活動。 薬機法・景品表示法・健康増進法の知識も生かしながらさまざまなライティング活動を行っている

