最近メディアなどで、HSPについて取り上げられることも増えてきました。
ただ、このHSPには色々な特徴があります。まだまだ解明されていないところも多い分、憶測などで間違った捉え方をする人もいるようです。
この記事では、改めてHSPと医療の関わり方、考え方などについて説明していきたいと思います。
最近よく聞く「繊細さん」。どんな人のこと?
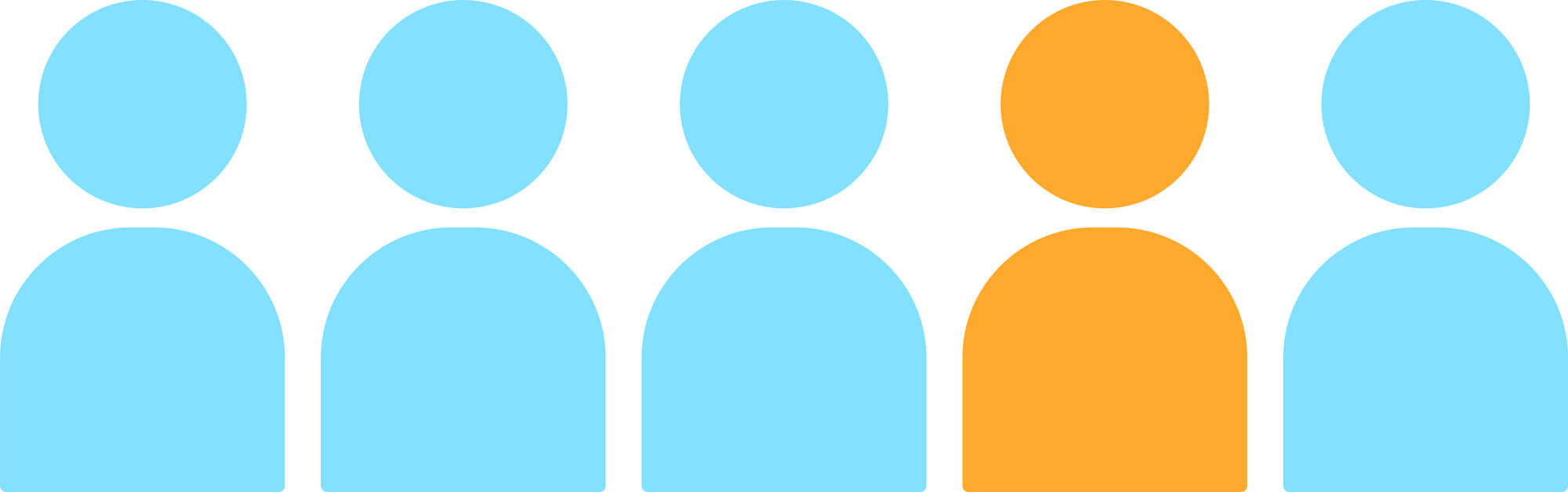
HSPとはHighly Sensitive Personの頭文字をとったもので、日本語では“繊細さん”などと表現されることが多いです。もう少し具体的に説明すると、環境刺激に対する感受性が豊かな人のことを指すといっていいでしょう。
そしてHSPを提唱したアーロン博士は、HSPの人は5人に1人の割合だと提言しています。イメージとしては感受性が豊かな人のうち、上位20%に入るような人をHSPさんであると定めたと考えると分かりやすいかもしれません。

この感受性は生まれもった気質なので、簡単に変わることはありません。気質というのは、アボガドに例えると真ん中にあるどっしりとした種のことです。これは外的な要因によって変わることがないことを示しています。
気質とよく似た言葉として性格がありますが、これはアボガドの種の周りにある果肉のイメージです。性格は遺伝的なことや環境などの外的な要因によって大きく変わる可能性を秘めています。どのような人と出会うのか、どのような体験をするかによって性格は変わっていくものなのです。
ようするに、HSPというのは気質の問題なので安易に変えることができないと考えられています。「根性がない…」「精神力が足りない…」わけでは決してなく、自分を責めて考える必要はありません。
HSPの4つの特徴
この感受性が豊かなHSPさんにおいては、DOESといわれる4つの特徴があります。このDOESとは、HSPの特徴を英語表記した時の頭文字です。
「D」はDepth of processingであり、1つの物事に対して、深く処理したり考えたりすること。
「O」はOverstimulationであり、些細な刺激に対しても過剰に受け止めてしまうこと。
「E」はEmotional response and empathyであり、何事に対しても共感性が高く、感情が動きやすいこと。
「S」はSensitivity to subtletiesであり、些細なことにも敏感に気づいて反応することです。
「HSP」は病気?悩みや困りごと、原因は?

HSPは生まれ持った気質であり、病気ではありません。それに感受性の高さが上位20%だと言われても明確な線引きがあるわけではないので、「HSPであるかどうか」と白黒で判断するのは難しいのが実情です。
自分でHSPとしての気質があるかどうかを考え判断するのが一般的ですが、この気質で悩ましい生活を送ることがあります。
先述のDOESの4つの特徴だけをみると「何か悪いことがあるのかな?」と感じる人もいるかと思います。たしかに4つの特徴はいい面もあるのですが、それだけではありません。
「D」に関する困りごと
例えば「D」にあたる特徴は、ものごとを思慮深くとらえる素晴らしい側面がある一方で、色々な側面から考察したり悩むためにそれだけ取り掛かるのに時間がかかります。
また常に最悪のケースを想定して、事前にそれが起きた時の被害が大きくならないように対策してからではないと、先に進めない特徴もあります。とくに仕事であれば周りと足並みをそろえる場面もあるでしょうが、それが上手くできずに困ることもあります。
「O」に関する困りごと
「O」は些細な刺激を敏感に感じるので、「蛍光灯に反射する白い紙がまぶしくて見ることができない」「時計の秒針が進む音が大きく感じ、気になってしまって眠れない」などの困ったことが起こりやすいと言われています。
「E」に関する困りごと
相手の気持ちに共感できるのはとても素晴らしいことです。ただ、相手のネガティブな気持ちも、あたかも自分が感じているかのように共感しすぎてしまい、辛い気持ちになって涙が止まらないこともあります。
「S」に関する困りごと
他人が髪を切ったことなどの変化にすぐ気がつきますが、話をしている時に相手の表情が微妙に変わったことにもすぐ気がつきます。そのため場の空気を読み過ぎてしまって、過剰に相手に気を使ったりしてヘトヘトに疲れ切ってしまいます。
HSPと似た特徴を持つ病気や症状は?
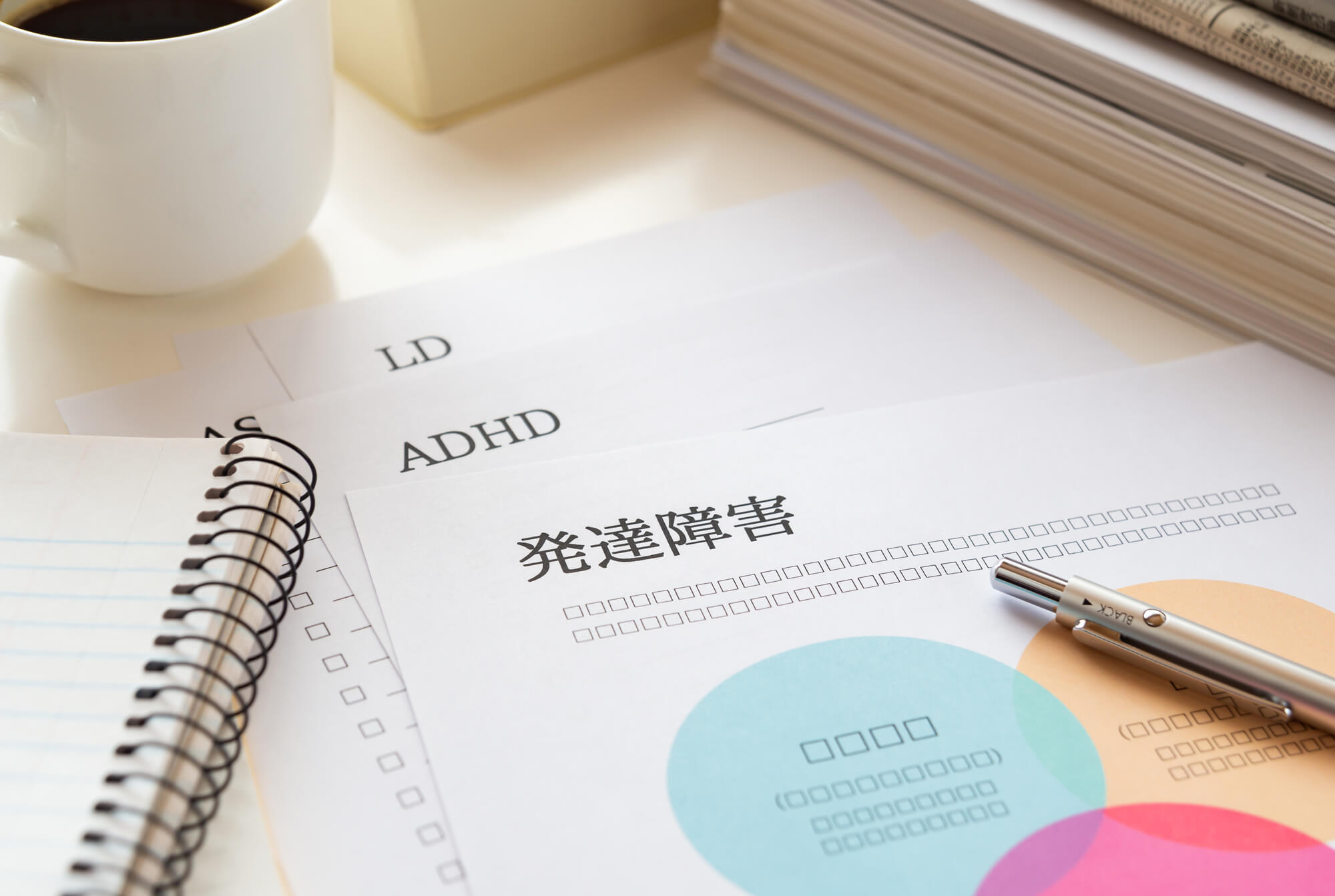
HSPと発達障害の類似性が指摘されることがあります。HSPは病気ではないので、発達障害と全く別のカテゴリーであり比較することはできません。しかし当事者としては、ともに共通するような特徴もあります。
例えば、ともに不注意という特徴を持っていることがあります。ADHD(注意欠如・多動性障害)の特性がある人は、ポンポンと興味が移るので頭の中が多動になってしまい、集中力が続かずに不注意の症状を呈することがあります。
一方でHSPさんも先述のように、1つの物事を深く考えて没頭してしまうがゆえに、周りが見えなくなって結果的には不注意に至るケースがあります。
また、HSPさんはASD(自閉症スペクトラム障害)の特性がある人と同じように、頑固で融通がきかないように見えることもあります。たとえばHSPさんは効率のいい仕事のやり方を教えてもらっても、最悪の事態を想定してからじっくりと物事に取り組むなど、自分のペースを大切にすることがあります。
このようにHSPは発達障害の特性と似た点もあるのですが、大きく違うところもあります。それは空気の読み具合です。発達障害の特性がある人は、時に空気を読めない言動をして人間関係に摩擦を起こすことがありますが、HSPさんの場合は過剰に周りの空気を読んで、相手が望んでることを先回りして行うような人なので、周りからは“いい人”と思われていることが多いです。
HSPと発達障害は類似点も相違点もあるため、HSPを提唱したアーロン博士ですら HSPと発達障害が全く別物とは言及しておらず、裏と表の関係に近いのではないかと考える専門家もおられます。
大人のADHDってなに? 特徴を知って上手な付き合い方を知ろう
HSPとの向き合い方やつらいときの対処法
HSPは病気ではないので、いかにその気質とうまく付き合うかが大切です。たとえば、HSPさんは刺激を敏感に感じすぎるがゆえにパーソナルスペースが広い人が多いため、物理的な距離を取るように心がけてください。
具体的には、立っている時なら半歩下がってみたり、座っている時なら椅子に深く腰掛けて背筋を伸ばすようにするだけでも人との距離を取ることができます。
さらに共感力が強いHSPさんの場合は、隣の人がイライラしてる感情がまるで自分にぶつけられているような感覚になり、その場にいるのがいたたまれなくなります。
このような時は、できる限りその刺激が自分に届かないように、相手と自分の間に透明なアクリル板があると想像してみましょう。その刺激をブロックする感覚です。他にも、実際に目の前にある机の上のティッシュBOXやペンケースなどを境界線だと考え、それ以上に自分のところに刺激が入ってこないようにセーブする方法もあります。
井上先生からのアドバイス

HSPは病気ではないにしろ、当事者が困っていることは事実なのです。病気じゃないから問題がないというわけではありません。
当事者の声に耳を傾けて、周りの人がどのようなサポートをすればいいのかを共有できるようになればいいですよね。
プロフィール

- 監修:医師 井上 智介
- 島根大学を卒業後、様々な病院で内科・外科・救急・皮膚科など、多岐の分野にわたるプライマリケアを学び臨床研修を修了する。 平成26年からは精神科を中心とした病院にて様々な患者さんと向き合い、その傍らで一部上場企業の産業医としても勤務している。

