2017年3月22日(水)、スウェーデンで行われた嗅覚の最新研究によって、嗅覚の低下と健康リスクの関係性について発表されました。(参考)
普段あまり意識することのない嗅覚かもしれませんが、出来たら、若いうちから嗅覚が衰えないように「においを意識した生活」をおくりたいものですね。
今回は「嗅覚」について、最新研究結果をもとに、老化した場合のリスクや予防法などを耳鼻咽喉科の岡田先生に詳しく解説していただきました。
□ スウェーデンで行われた嗅覚の最新研究
□ 嗅覚が老化する原因
□ 嗅覚が老化した場合の健康リスク
□ 嗅覚を若返らせる方法
□ 嗅覚の老化を自分で簡単にチェックする方法
□ 最後に編集部から一言

2017年3月22日(水)、スウェーデンのストックホルム大学で40代から90代を対象に、10年にわたって行われた嗅覚に関する研究が発表されました。
対象者は1800人弱にも及び、嗅覚の低下と死の危険性の関連性について述べられております。
観察期間の10年間で全体の23%が死亡し、嗅覚が正常な人は、嗅覚の低下がみられた人よりも死亡率が8%も低かったことが示されました。
また逆に、嗅覚の低下がみられた人は、嗅覚が正常な方よりも19%も死の危険性が高かったことが示されました。
スウェーデンで行われた研究の他にも、嗅覚が低下した人の5年後の死亡率は高かった、死の危険性は3倍上がる、など嗅覚の低下と健康のリスクに関連した報告がみられています。
今後、嗅覚というものが重要な生命のマーカーとして注目されていく可能性があるかもしれません。
《参照》
・Eurek Alert
・PubMed
30歳前後をピークに嗅覚は少しずつ衰えていきます。他の感覚器に比べると、遅いですが、70~80歳には嗅覚の低下を自覚する方が多いです。
鼻炎や副鼻腔炎などによって鼻がつまり、においの刺激がにおいの感覚細胞に届かないと機能が落ちるのが早くなります。
すぐに機能が悪くなるわけではありませんが、何十年もかけてにおいの刺激が届かないことによります。
脳にとっては不快な香りのため、情報をブロックしてしまいます。
また、嗅覚細胞の障害を早める可能性があります。
20~30日で新生と細胞死を繰り返している嗅覚細胞ですが、疲れやストレスが多いと正常なサイクルを保てなくなります。
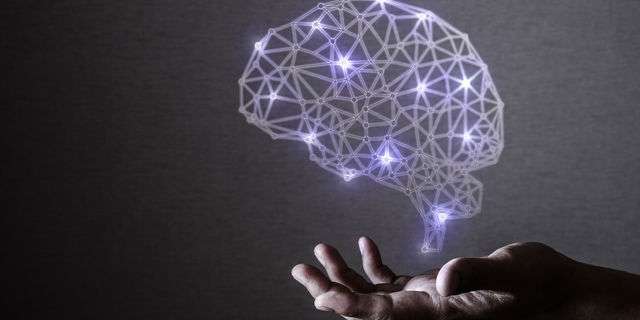
60歳以上の方に多い、物忘れの症状から始まる認知機能の低下を主体として病気です。初期症状として、においの低下が指摘されています。

50歳以上の方に多い、手足の震え、筋肉のこわばり、歩きづらくなるなどの症状が主体です。
アルツハイマー病と同じく、初期症状としてにおいの低下が起こりうる場合があります。

においや風味が分からず、食事を美味しく感じにくくなり、生活の活力に支障が出てしまいます。
ヨーロッパでは、においの素を使ったリハビリテーションで効果を上げています。においをもった物質を1日2回、色々なにおいをローテーションしながら嗅ぐと、嗅覚の回復が良くなります。
また、スニフ・セラピーといった鼻でにおいをよく嗅ぐ行為も効果的です。
「心地良いと思うにおい」を数種類用意して、年に数回嗅いでみて点数を付けてみたり、花を育てながら、毎年花のにおいを楽しみつつ季節を感じてみたりする方法が有効と考えられます。
近年、嗅覚に対する研究が非常に活発で、新たな知見が毎年のように出ています。
最も効果的な方法は、ご紹介した通り、好きな食べ物や花など、においを楽しみながら過ごされるのが1番です。
楽しみながらにおいを感じることによって、脳にとっても良いサイクルとなり、より、嗅覚の低下を予防できると思います。
(監修:耳鼻咽喉科 岡田先生)

普段あまり意識することのない嗅覚かもしれませんが、出来たら、若いうちから嗅覚が衰えないように「においを意識した生活」をおくりたいものですね。
今回は「嗅覚」について、最新研究結果をもとに、老化した場合のリスクや予防法などを耳鼻咽喉科の岡田先生に詳しく解説していただきました。
目次
□ スウェーデンで行われた嗅覚の最新研究
□ 嗅覚が老化する原因
□ 嗅覚が老化した場合の健康リスク
□ 嗅覚を若返らせる方法
□ 嗅覚の老化を自分で簡単にチェックする方法
□ 最後に編集部から一言
スウェーデンで行われた嗅覚の最新研究

研究内容
2017年3月22日(水)、スウェーデンのストックホルム大学で40代から90代を対象に、10年にわたって行われた嗅覚に関する研究が発表されました。
対象者は1800人弱にも及び、嗅覚の低下と死の危険性の関連性について述べられております。
研究結果
観察期間の10年間で全体の23%が死亡し、嗅覚が正常な人は、嗅覚の低下がみられた人よりも死亡率が8%も低かったことが示されました。
また逆に、嗅覚の低下がみられた人は、嗅覚が正常な方よりも19%も死の危険性が高かったことが示されました。
長谷川先生の考察
スウェーデンで行われた研究の他にも、嗅覚が低下した人の5年後の死亡率は高かった、死の危険性は3倍上がる、など嗅覚の低下と健康のリスクに関連した報告がみられています。
今後、嗅覚というものが重要な生命のマーカーとして注目されていく可能性があるかもしれません。
《参照》
・Eurek Alert
・PubMed
嗅覚が老化する原因

加齢
30歳前後をピークに嗅覚は少しずつ衰えていきます。他の感覚器に比べると、遅いですが、70~80歳には嗅覚の低下を自覚する方が多いです。
鼻炎、副鼻腔炎
鼻炎や副鼻腔炎などによって鼻がつまり、においの刺激がにおいの感覚細胞に届かないと機能が落ちるのが早くなります。
すぐに機能が悪くなるわけではありませんが、何十年もかけてにおいの刺激が届かないことによります。
たばこ、人工的な強い香り
脳にとっては不快な香りのため、情報をブロックしてしまいます。
また、嗅覚細胞の障害を早める可能性があります。
ストレスや疲れ
20~30日で新生と細胞死を繰り返している嗅覚細胞ですが、疲れやストレスが多いと正常なサイクルを保てなくなります。
嗅覚が老化した場合の健康リスク
アルツハイマー病
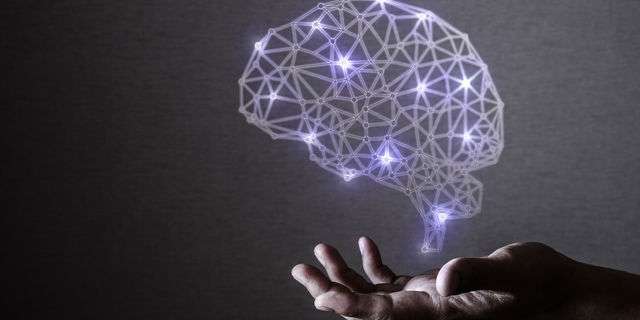
60歳以上の方に多い、物忘れの症状から始まる認知機能の低下を主体として病気です。初期症状として、においの低下が指摘されています。
パーキンソン病

50歳以上の方に多い、手足の震え、筋肉のこわばり、歩きづらくなるなどの症状が主体です。
アルツハイマー病と同じく、初期症状としてにおいの低下が起こりうる場合があります。
食事の味が感じにくくなる

においや風味が分からず、食事を美味しく感じにくくなり、生活の活力に支障が出てしまいます。
嗅覚を若返らせる方法

ヨーロッパでは、においの素を使ったリハビリテーションで効果を上げています。においをもった物質を1日2回、色々なにおいをローテーションしながら嗅ぐと、嗅覚の回復が良くなります。
また、スニフ・セラピーといった鼻でにおいをよく嗅ぐ行為も効果的です。
嗅覚の老化を自分で簡単にチェックする方法

「心地良いと思うにおい」を数種類用意して、年に数回嗅いでみて点数を付けてみたり、花を育てながら、毎年花のにおいを楽しみつつ季節を感じてみたりする方法が有効と考えられます。
最後に岡田先生から一言

近年、嗅覚に対する研究が非常に活発で、新たな知見が毎年のように出ています。
最も効果的な方法は、ご紹介した通り、好きな食べ物や花など、においを楽しみながら過ごされるのが1番です。
楽しみながらにおいを感じることによって、脳にとっても良いサイクルとなり、より、嗅覚の低下を予防できると思います。
(監修:耳鼻咽喉科 岡田先生)
プロフィール

- 監修:耳鼻咽喉科 岡田先生
- 1982年生まれ、2000年群馬県内の県立高校を卒業後、同年4月に私立大学医学部医学科に入学。2006年3月に同大学卒業後、研修医として市中病院を2年間勤務。その後、大学病院に勤務し、2010年4月、大学院に入学、頭頸部癌、感染症を主に基礎研究を行い、医学博士を取得。

